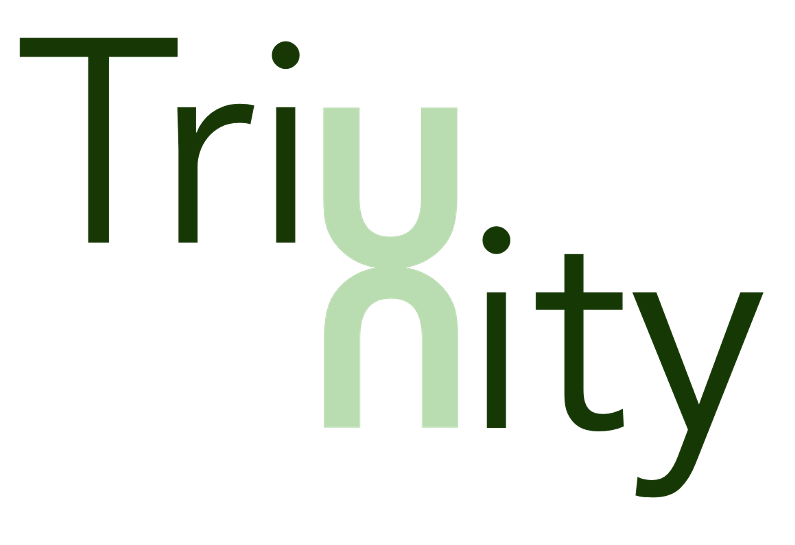-
京都から世界へ!中国人気カフェ「M Stand」が東山に初上陸、%Arabicaの成功に続くか?
By 鶴田 彬、2025年9月5日 1. Intro 先月、私の地元である京都に帰省していて街中をウロウロと歩き回っていると、街が以前帰省した2023年よりもはるかに国際的で外国人に優しい街になっているように感じられた。特に祇園周辺では、多くのレストランが外国人観光客向けに特化しているのは明らかで、昔よく通っていたお店などは無くなっていたり、景観が変わったからか道に迷うこともあった。また、ラーメン店の中には、日本人の好みに合わなそうというか、明らかに外国人観光客向けのお店もあるように見える。京都を訪れる外国人観光客は着実に増加していおり、2024年には京都市を訪れた外国人観光客が初めて1,000万人を超え、過去最高の1,088万人に達した。そして、外国人宿泊客の数は、日本人宿泊客を上回っている。そう考えると、外国人観光客をターゲットにすることは、賢明で理解しやすいビジネス戦略と言える。 Figure 1.2024年において京都の観光客が急増:外国人宿泊客数が日本人宿泊客数を上回る。 京都において、外国人観光客をメインターゲットに置くことは、何も地元ブランドだけに限ったことではない。最近、流行の中国コーヒーチェーン “M Stand(Mスタンド)” が、人気の観光地である南禅寺近くに海外初店舗をオープンした。なぜ、京都が海外第一号店の場所に!?と思う方も多いかもしれないが、これにはM Standの戦略的意図が反映されている。この印象的なデザインの店舗を訪れると、店内の客層は主に中国人観光客をはじめとする外国人観光客で、地元の日本人客は多くない。これは隣接するBlue Bottle Coffee (ブルーボトルコーヒー)の店舗とは大きく異なり、独自のマーケティング戦略によるものと思われる。 M Standのアプローチは、もちろん中国人旅行者をターゲットとしたディアスポラ・マーケティングの要素を取り入れているように見えるが、彼らのビジョンはより大きいように見える。これは、京都を起点に多様なグローバル顧客層を獲得することを目的とした、より先見性のある戦略を示唆している。この記事では、M Standの京都進出を紹介しながら、京都でグローバルなブランディングをすることの意味・インパクトを述べていこうと思う。(ディアスポラ・マーケティングに興味のある方はこちらの記事もご覧ください。:海外在住外国人コミュニティ:“ディアスポラ”は海外進出の際のゲートウェイになる) Figure 2. M Standの海外第1号店が京都にオープン 2.グローバルにブランディングしていく上での京都の魅力・利点 日本の古都である京都は、日本人の方なら言うまでもなくご存じだと思うが、外国人の方々にも豊かな歴史と美しい景観で知られている。春は桜、夏は緑豊かな自然、秋は鮮やかな紅葉、冬は静謐な雪景色と、象徴的な歴史的建造物に囲まれながら、一年を通して訪れる人々を魅了している。かつ、舞妓や禅といった独特の文化的要素も、この洗練された街の特徴であり、これらのポジティブなイメージが京都を拠点とするブランドと結びつき、ブランドイメージを向上させる機会を提供することになる。外国人の消費者に京都発のブランドですと紹介して、あー低品質のサービスの悪いブランドかもねという印象を抱かれることはないのは感覚的にわかるだろう。 FIgure 3. 京都の四季折々の景観 出典: “京都観光Navi” and “絶景に行こう!!” 京都は世界中から観光客を惹きつけるので、京都のブランドは多様な消費者にリーチし、グローバルなブランド認知度を高めることが出来る。京都市産業観光局によると、最も多い観光客は中国人で、次いでアメリカ、韓国、オーストラリア、イタリア、フランスからの観光客が続いている。京都は中国ブランドにとって、出店する上で魅力的な場所と言えよう。自社ブランドに馴染みのある中国人観光客をターゲットにすることで、最小限のマーケティング努力で即座に収益を上げることができ、同時に、他の海外からの観光客や日本の消費者にも自社ブランドを宣伝し、将来のグローバル市場への進出の基盤を築くことが可能だからだ。 Figure 4.2024年の京都市における外国人宿泊者数の出身地域別割合 グローバルに店舗を展開しているカフェチェーンである% Arabicaは、ローカルのベンチャーから国際ブランドへと変貌を遂げた、マーケティングの成功例と言えるだろう。香港で日本人起業家、東海林克範氏(Kenneth Shoji)によって設立されたこのブランドは、京都の東山に旗艦店をオープンしたことで大きな注目を集めた。この戦略的な動きが% Arabicaの幅広い認知度獲得へとつながり世界各国への進出をもたらし急速な成長を後押しした。 Figure 5. 京都東山の%Arabicaストア…
-
【2025年版】シンガポール飲食業の規制ガイド:外国企業が知っておくべきポイント
By 钱 俞颖, 2025.06.20 中国の中小企業からシンガポール市場への参入に関する問い合わせがますます増えていることを受け、シンガポールの関連規制に関する実践的なヒントと、中国企業を例に扱いながら、それらに関する知見を共有することにしました。これらのヒントは、中国企業だけでなく、シンガポール市場に新規参入する、、大手多国籍企業を含む、他の外国企業にも役立つと考えますので日本語版でもシェアさせていただきます。以下、記事をご覧ください。 シンガポールにおける中国の食品・飲料チェーン店の参入状況 周知の通り、シンガポールは、地理的な近さ、文化的な類似性、そしてビジネス優遇政策を背景に、中国企業によるASEAN進出の拠点として好まれている。2024年6月末時点で、35の中国食品・飲料ブランドがシンガポールで191店舗を展開している。特に2023年以降には、COTTI Coffee、Luckin Coffeeなど、15の新規ブランドがシンガポールに進出している。(Luckin CoffeeとCOTTI Coffeeの海外展開については、こちらの記事もご覧ください:中国カフェチェーンの海外進出“Grab-and-Go”でシェア拡大を狙え) シンガポールにおける中華系飲食店のタイプは多様であるものの、カジュアルなダイニングや飲料への偏りがある。Luckin CoffeeやMIXUEといった飲料店(コーヒー・紅茶専門店)が全体の48%を占め、最も大きな割合を占めている。次に多いのは、主に火鍋などのメイン料理で、四川料理や中国北部の料理を提供する店が多く、シンガポールの中華系飲食店の27%を占めている。(東南アジアにおける新しいスタイルのティーブランドのサプライチェーンについては、こちらの記事をご覧ください。: 新式茶のグローバル展開: サプライチェーンの最適化が成功の鍵 (MIXUE, HEYTEA, CHAGEE, ChaPanda)) Figure 1:シンガポールにおける中国の食品・飲料ブランドの内訳 中華料理への需要が持続し、市場環境も好調なことから、中華系食品・飲料チェーンはシンガポールで引き続き成長していくと見込まれている。その大きな原動力の一つは、シンガポールに多数居住する華僑の存在になる。2024年6月現在、シンガポール国民の75.6%は華僑である。また、シンガポールは中国人観光客に人気の旅行先となっており、2024年には中国本土から308万人が訪れ、前年比126%増を記録し、昨年のシンガポールへのインバウンド観光客総数の18.7%を占めると推定されている。中国人観光客からの大きな需要と、華僑シンガポール人の間で高い受容度を誇ることから、中華系食品・飲料チェーン店がシンガポールに進出するのは、比較的容易であると結論づけられる。 Figure 2: シンガポールに進出したLuckin Coffeeのとある店舗 しかしながら、シンガポールで食品・飲料チェーン店を開業するには、いくつかのリスクが伴う。その一つが各種の規制遵守になる。 コンプライアンスのための主要な規制 シンガポールでは、食品・飲料事業は規制や法律によって非常に厳しく規制されており、食品安全、衛生基準、労働法など、様々な側面が規制されている。 シンガポールでレストランやコーヒーショップを開業する際に、企業が注意すべきコンプライアンスは基本的に3タイプに分類できる。それは以下の通りである。 a. 市場参入におけるコンプライアンス シンガポールで外国人がレストランや喫茶店・カフェを開業することに関して、特別な制限はない。外国人は、会計企業規制庁(ACRA)に直接会社を登録し、レストラン経営に必要なライセンスを取得することができる。 一般的に、シンガポールで食品店のライセンスを申請することはそれほど難しくなく、各部門が提供する手順に従って、GoBusiness Portalで申請するだけである。 Figure 3: 食品店に適用される一般的なライセンス 現地居住要件 / Local…
-
新式茶のグローバル展開: サプライチェーンの最適化が成功の鍵 (MIXUE, HEYTEA, CHAGEE, ChaPanda)
By 钱 俞颖, 2025.05.13 2025年初頭、中国の新式茶(ニュースタイルティー、新感覚ティー)ブランド3社、Good Me(古茗)、MIXUE(蜜雪冰城)、CHAGEE(霸王茶姬)が香港と米国で上場した。新式茶業界における上場数の急増は、中国の新式茶市場における熾烈な競争を示唆している。中国チェーンストア&フランチャイズ協会(中国连锁经营协会)が発表した報告書によると、中国の新式茶市場は2025年に2,010億人民元に達すると予想されている一方で、市場の成長率は2023年の44%から2024年には19.7%に低下している。 Figure 1. 中国における新式茶の市場規模と成長速度 「競争が激しすぎて、ある意味ではIPOが最後のチャンスかもしれない」と、オンライン小売メディアLingshouke(灵兽传媒)の食品・飲料アナリスト、Shi Li氏は述べている。(競争激しい中国の新式茶市場についてはこちらの記事もご参照ください: MIXUE (蜜雪), HEYTEA (喜茶), Chagee (霸王茶姫), etc. 中国の新式茶とは?-新式茶市場における新たなトレンドを分析-) 中国市場がレッドオーシャンへと移行する中、大手ブランドも戦略を転換し、海外市場への注力を強化している。様々な新式茶ブランドが、様々な地域でポジションを築き始めている。 MIXUEやCHAGEEなど多くのブランドが、地理的な近さ、暑い気候による飲料需要、そして中国ブランドの受容度の高さなどを理由に、最初の進出地として東南アジアを選択している。MIXUEは2024年末までに東南アジア地域で約4,800店舗を展開し、中国で展開する低価格モデルを模倣・実施することでインドネシアとベトナムで大きな成功を収めている。そして、CHAGEEは、スターバックスをベンチマークとして、マレーシアとシンガポールで高級ミルクティーブランドとしての地位を確立しつつある。 一方で、ChaPandaは、コーヒー文化が支配的な韓国市場に挑戦しており、HEYTEA は北米や英国などの高級市場に重点を置いている。(HEYTEAの海外市場展開については、以下の2つの記事もご参照ください。: 海外在住外国人コミュニティ:“ディアスポラ”は海外進出の際のゲートウェイになる ; 新式茶会の先駆者HEYTEAは日本の消費者をインスパイアできるのか?-日本初、HEYETA大阪店を紐解く-) Figure 2. 2024年までの主要ブランドの海外店舗数 最終的に誰が勝者になるかは未だ分からないが、新式茶ブランドが世界展開の初期段階で直面する最大の課題の一つは、サプライチェーンに関すものになるだろう。主要原材料を中国からの供給に頼ると、コストが大幅に上昇してしまうという課題がそこにはある。 Figure 3. 中国における新式茶サプライチェーンの概要 原材料の中で、特に重要なものはフルーツである。これが、新式茶と従来の茶系ドリンクの大きな違いの一つになる。原材料費は通常、フルーツティーの総コストの最大40%を占める。その中で、フルーツのコストは、全体の原材料費の約45%を占めており、茶葉、牛乳、トッピングなどの他の原材料と比較して最もコストのかかる材料となっている。 Figure 4. 新式茶の定番商品グレープチーズティー(多肉葡萄)の原材料コストの内訳 したがって、コスト削減には強力なフルーツサプライチェーンの確立が不可欠になる。中国国内では、大手ブランドは主に南部の省に農園を設立している。例えば、MIXUEは四川省と重慶市にレモン農園を構えることで、レモンの調達コストを1kgあたり4元から1元にまで削減した。(*MIXUEの中国国内での人気主力商品の一つはレモネードである。) Figure 5.…
-
MIXUE (蜜雪), HEYTEA (喜茶), Chagee (霸王茶姫), etc. 中国の新式茶とは?-新式茶市場における新たなトレンドを分析-
By 鶴田 彬 & 钱 俞颖, 2025.04.15 Intro 前回の記事「新式茶会の先駆者HEYTEAは日本の消費者をインスパイアできるのか?-日本初、HEYETA大阪店を紐解く-」では、HEYTEAの日本市場への海外進出に関する分析について書きました。この記事を読んでいただきフィードバックを提供してくださった多くの読者の方々に心より感謝申し上げます。そして、ほとんどの日本人の読者の方にとっては、「新式茶」というワードに馴染みがないこと、そのような商品カテゴリーが中国市場でどのような存在感を放っているのか、基本的な情報が行き届いていないことを実感しました。新式茶(ニュー・スタイル・ティー)は、中国のフードチェーンブランドがいかにクリエイティブかを表した象徴的なものであり、世界の食品市場という視点から見てもイノベーションと捉えることができます。本記事では、中国の新式茶市場の概要を述べ、現在のトレンドを分析し、国際的に成功する可能性のあるブランドを考えながら解説できればと思います。 1. 新式茶とは(定義) 伝統的な茶飲料と比べて、新式茶は主に18歳から35歳の女性を含む若年層、特にZ世代に向けて提供されていると言え、私のような中年男性がこれらの商品に初めて出会うと、創造的すぎる、斬新すぎると感じてしまうかもしれない。実際に、私は初めてチーズティーを見た時は面を食らった。ひとえに新式茶と言っても様々な種類があるので、まずは新式茶のの定義を見てみよう。中国連鎖経営協会(中国连锁经营协会)のグループ基準「新茶飲術語和分類」によると、「新式茶飲料は、原葉茶や茶の抽出物と、果物、搾りたての果物や野菜ジュース、果汁100%ジュース、野菜、乳製品といった材料を組み合わせて作られる飲料である。これらの飲料には他の食品添加物を含むことがあるものの、固形飲料ミックス(パウダーなど)は含まれておらず、現場で準備・加工される。」と定義されている。 Figure 1. 組み合わせ次第で無限に広がる新式茶の種類 出典: 中国新茶饮供应链白皮书 2024 もう一度言い直すと、新式茶は、従来の茶葉または抽出液をフルーツ、ジュース、野菜、乳製品と組み合わせた飲み物で、固形ミックス・パウダーを使用せずに店舗・その場で準備された飲み物ということである。これらの原材料と加工方法に基づいて、新式茶の飲料は、フルーツティー、フレッシュミルクティー、バブルティー、コールドブリューティー、ミルクティーの5つのタイプに分類できる。とはいえ、消費者の頭の中では、大まかに言って、フルーツティーかミルクティー(タピオカティーを含む)の2つの選択肢に分別され、夏にはフルーツティーが好まれ、冬にはミルクティーが好まれる。消費者は、甘さのレベルを調整したり、タピオカパールなどさまざまな具材を追加したりして、自分好みに飲み物をカスタマイズすることができる。 Figure 2. 新式茶の多様な種類 出典:各種ブランドのWeChat ミニプログラム 2. 新式茶発展の過程 長年にわたり、新式茶業界は大きく成長し、現在では中国において消費者の関心が高いメインの市場となっている。 中国新茶飲料サプライチェーン白書 2024 (中国新茶饮供应链白皮书 2024)によると、1980年代から1990年代にかけて、タピオカティー・ミルクティーが台湾海峡を挟んだエリアで、若者たちに美味しくて手頃な価格の飲み物として提供され始め人気となった。2015年頃になると、HEYTEAや茶颜悦色(Sexy Tea)などのスタートアップ企業が、ティーパウダーやクリーマーの代わりに新鮮に抽出したお茶を使用して、ミルクティーを作り始め、高品質で風味豊かな体験を提供し始めた。この革新により、現在「新式茶」として知られるものが誕生した。 2022年までには、多数の大規模なチェーンブランドが製造および販売の分野に参入し、製品の品質だけでなく、ブランドのパッケージングやデザインを向上させた。その結果、顧客一人当たりの支出も大きく増加した。2023年からは、ブランドはサプライチェーンを合理化し、先進技術を活用することで新式茶を更にグレードアップしている。これにより、味、品質、新鮮さ、健康への配慮、透明性、そして費用対効果を向上させることが可能となり、さまざまな文化をお茶に融合させることで、ひとつの飲み物が消費者のライフスタイルに影響を与えることができるまで商品が成長したと言える。現在、中国全土に新式茶の多くのブランドが広がっており、その結果として、スターバックスのようなコーヒーブランドは多くの新式茶ブランドと競争しなくてはならず、スターバックスが中国で苦戦していると言われる理由の一つとなっている。 Figure 3. 2023年半ば頃における中国の美団プラットフォームにおけ飲料店数のシェア 出典: 中国新茶饮供应链白皮书 2024 3.…
-
新式茶会の先駆者HEYTEAは日本の消費者をインスパイアできるのか?-日本初、HEYETA大阪店を紐解く-
by 鶴田 彬、2025.3.17 前回のブログでは、海外のビジネスパーソン向けに、日本の消費者は、食べ物や飲み物に控えめで自然な甘さを求め、過剰な砂糖を避けていることについて説明し、そのブログを日本語でも共有した。その中で、中国では主流の飲み物として定着化した新式茶・ニュースタイルティーのフルーツティー、とりわけHEYTEAのような高品質・健康志向のアプローチを取るブランドは、日本の消費者に歓迎される可能性があることを示唆した。そんな中、2025年2月、HEYTEAは大阪のDOTONプラザに日本初の店舗をオープンした。今回は、HEYTEAの紹介と日本でのマーケティング戦略について分析してみようと思う。(前回のブログはこちらから:“砂糖は嫌いだが甘さは好き”-ワガママな日本人消費者の好みにどう対応するか) Figure 1. 日本初のHEYTEAストアは大阪にオープン 1. HEYTEAについて Figure 2.HEYTEAの商品イメージ 日本人の多くはこのHEYTEAというブランドに馴染みがないだろうが、中国ではHEYTEAは新式茶・ニュースタイルティーのリーダーとして、市場に君臨しているといっても過言ではない。若手創業者の聂云宸(Nie Yunchen)氏によって、2012年より広東省江門市からスタートした(当時の名前は皇茶)中国茶をモダンスタイルで提供するブランドであり、パウダーなどは使用せず、店舗で茶葉からお茶を入れ良質の商品を提供することに重点を置いている。当初のターゲット層としては、20~30歳、特に20~25歳ホワイトカラーワーカーが想定されており、開発されたフルーツとチーズフォームをブレンドしたチーズティーが若い女性を中心に口コミで広がり2017年より店舗数を伸ばし一大ブームを巻き起こし、今や新式茶会のスターバックスと見られるほどに中国の市場に定着したブランドである。(余談だがCEO聂氏がスターバックスをベンチマークしていない点も面白い点である。) Figure 3. HEYTEAのチーズティーは、中国で一大ブームを巻き起こし行列を産んだ HEYTEAのブランドは、“Tea of Inspiration(灵感之茶)”をコンセプトに、文化体験を提供するブランドと位置付けることができ、現代と伝統の融合された革新的な商品・ストアデザインが若者に評判を受けている。また、一部で。「ミルクティーで時間を無駄にするデザイン会社」と冗談めかして呼ばれることもあり、マーケティングコンテンツのデザインに中国の美学、禅、ミニマリズム、レトロな要素を取り入れることで、幅広い若い消費者にアピールすることに成功し、現在、総店舗数は4,000店を超えている。また、最近、クオリティを維持するために2022年に開始したフランチャイズ展開を廃止したことでも話題に上がっている。 Figure 4. HEYTEAの革新的な商品ラインナップ 出典:HEYTEA GO WeChatミニプログラム 商品メニューを見れば、タピオカミルクティーに加え、チーズティーやフルーツティーなどバラエティに富み、HEYTEAの強みの一つが商品開発にあることがわかる。そんな、これまで日本市場で見られることとの無かったと言えるクオリティ重視の新式茶HEYTEAが日本で受け入れられる土壌があるのか見ていこう。 2. 中国市場とは勝手が違う 2-1.ライバルであるコーヒー文化の浸透度が異なる コーヒー文化が広まり、浸透度が深ければ深いほど、新式茶の市場参入は困難になる可能性があり、中国市場と日本市場の大きな違いはコーヒー文化の普及度、そのヒストリーにあるだろう。日本の消費者は、1960年代からコーヒーと長く付き合ってきたため、新式茶が日本で定着するのはより困難と考えられる。以前のブログ中国カフェチェーンの海外進出“Grab-and-Go”でシェア拡大を狙えでも述べたが、上海では、スターバックスがすでに市場に参入していたがコーヒーの市場への浸透度はLuckin Coffee登場まではそこまで強くなかったと感じており、私の教室では一点点のようなバブルティーがデリバリーで注文をよくされていた。(中国は、1999年に北京からスターバックスに参入したが、コーヒーをデイリーで飲み始めたのは、Luckin Coffeeなどが台頭してきた2020年前後と言えるだろう。)その後、Luckin Coffeeの登場で市場は変容していくのだが。上海の消費者の体感としては、Luckinのようなコーヒーチェーンと新式茶のスタンドがほぼ同時に登場したイメージであり、日本とは市場参入時の状況が異なる。HEYTEAは日本市場では、よりスターバックスやブルーボトルなどのカフェとの厳しい競争に直面することになるだろう。その点において、日本市場への参入は、中国や他のアジア地域よりも困難であるように思われ、ヨーロッパなどの西洋市場に近いものと考えられる。 2-2.そもそも味の好みが違う 中国人消費者と比べると、殊更お茶に関しては、日本の消費者は伝統的または単調な好みを持っていることが多く、中国の消費者ほど複雑にブレンドされた味に慣れていないと懸念されている。最近は上海で、多くの消費者が、烏龍茶ベース・ジャスミン茶ベースのミルクティーを飲むのだが、紅茶を除く中国茶や日本茶に牛乳や砂糖を入れて飲もうと言う習慣は、多くの日本人は持っていないと言えるだろう。そして、これは、チーズティーなどの革新的な製品を日本市場に導入する際に課題となる可能性がある。上海で、私は日本人の友人と初めてチーズティーに出会ったとき、最初はためらいを感じ、そのアイデアに少し違和感を覚えたし、チーズティーを自身のチョイスにすることから遠ざけていた。後に、中国人の友人の勧めで試してみると(私があまりにも躊躇うので身叶えて奢ってくれた。)、実際には非常においしいことがわかり、すぐにファンになったのが、この最初に商品をトライさせるコスト、他商品からこちらを選択させるスイッチングコストが日本では高くなるだろう。 Figure 5. Luckin Coffeeのジャスミンミルクティー(鲜萃轻轻茉莉) 2-3.…
-
“砂糖は嫌いだが甘さは好き”-ワガママな日本人消費者の好みにどう対応するか
By 钱 俞颖, 2025.01.21 前回の記事:海外在住外国人コミュニティ:“ディアスポラ”は海外進出の際のゲートウェイになるで少しローカライゼーションについて話しましたが、今回の記事はそのローカライゼーションに焦点を当てています。 日本人の方は、海外旅行をする際にまたは輸入食品を手にした際に、甘すぎると感じたことはないでしょうか? 本稿の記事は、飲食品産業に従事する中国人ビジネスパーソン向けに執筆したものになるのですが、中国人アナリストが日本市場の甘さに関する嗜好をどのように分析しているのかを理解することは、日本の飲料ブランド・飲食産業の方にとっても中国市場との違いを知る上で、何か気付きに繋がるのではないかと考え、日本語版をシェアすることにさせていただきました。ちなみに、執筆中にお米の甘みについて議論しましたが中国人スタッフは、その甘さを理解できず、しばらく噛むと、少し甘さを感じるといった日本人の話は伝わりませんでした。 以下、本文になります。お楽しみいただければと思います。 日本市場の無糖飲料の市場浸透率は中国市場の10倍 日本に行ったことがある外国人なら、自国のお店と比べて、日本のコンビニや自動販売機に無糖や低糖の飲み物が溢れていることに気づくことになる。日本人との会食では、飲酒を除けば、ほとんどの日本人男性は無糖の飲み物を選ぶ傾向がある。日本の砂糖入り飲料の市場シェアは、1980年以降減少し続けている一方で、無糖飲料の市場シェアは1980年の1%から2022年には54%へと急速に成長している。(参考までに比較すると中国における無糖飲料の市場シェアはわずか5%程度である。) アメリカ農務省(USDA)が2024年に発表した世界の砂糖消費量に関する報告書によると、日本の年間砂糖摂取量は1人当たり約14kg、中国は日本をわずかに上回る約16kg、欧州と米国は日本の 2〜3倍となっている。多くの日本人読者も感じておられるように、日本人の砂糖摂取量はほとんどの国よりも低いと結論づけることができる。(それでも14kgと言われるととてつもない量に感じられるのだが。) しかし、これは日本人が甘い食べ物・スイーツを好まないということでは全くない。 LINE Yahooが2024年に実施した15~64歳の日本人を対象としたスイーツに関する調査によると、日本人の90%以上がスイーツが好きと回答した。予想通りかもしれないが、Yesと答えた回答者の中では、男性よりも女性の割合が高く、10~30歳の若者の方が60代の中高年よりもスイーツを好むという結果が出た。 海外旅行などをしていると感じられると思うが、それぞれ国によって消費者の味覚は異なる。そして、それはその国の食文化と密接に関係している。私が上海で出会った日本人の多くは、上海料理や中国のミルクティー、デザートは甘すぎると言っていた。(上海料理については私も甘いと思う。)近年、Hey Teaなどの多くの中国の茶飲料ブランドが海外に進出しており、日本の消費者の嗜好を理解することが対日輸出向け商品の開発となって重要となっている。この記事では、中国の茶飲料を日本に輸出する際に、どのようにローカライズするかについてのヒントを与えられるように、日本のスイーツ・飲料市場についての私見を綴ろうと思う。 日本人は甘味に非常に敏感であり、60%以上の日本人は、“ほんのり甘い”食べ物を好む それぞれの国の人々によって「甘さ」に対する認識は異なる。オックスフォード大学の研究によると、日本人は甘味に対して特に敏感で、糖類などを大量に摂取しなくても甘味を感じられるということだ。これは日本人が子供の頃から微かに甘い味(米やみりんなど)に慣れ親しんできたことと関係があり、古代から現代の日本人の食生活にも同様の食習慣が受け継がれている。一方で、日本のメディアは長年にわたり糖尿病予防を推進し、「砂糖を摂りすぎると糖尿病になりやすい」という健康意識の種を日本人の心に植え付けてきた。 では、日本人は砂糖に対してどの程度敏感なのだろうか?飲食業界が実施した調査によると、中国人の約10%がブラックコーヒーを選ぶという、一方で、日本では、オンライン調査によると、63.5%以上の人がブラックコーヒーと無糖のお茶を選ぶことがわかった。 「砂糖・糖分の摂取に関して、最も気を付けていることは何ですか?」というアンケートでは、「糖分の少ない商品を選ぶ」を選んだ回答者が全体の39.9%であった。次いで「砂糖・砂糖分の多い食品・飲料を避ける」(26.3%)、「食品・飲料に一定量の砂糖・砂糖が添加されるのを避ける」(21.6%)となった。日本の無糖派は中国よりはるかに多いことがわかる。 Figure 1. 日本人消費者を対象にした糖分の摂取に関するアンケート結果 また、別の調査において、多くの方が人工甘味料に関する安全性を正確に理解していないこともあり、人工甘味料を好まないと回答したことは注目に値する。では、日本人にとって「低糖質・ほんのり甘い」食べ物とはどのような食べ物なのだろうか?それは、例えば、杏仁豆腐、ギリシャヨーグルト、パイナップルケーキ、そして以下に挙げる果物といった、それぞれ自然な甘みが含まれたものが該当するだろう。 Figure 2. 安宁(杏仁)豆腐 photo from: PROFOODS 外国企業は日本の消費者の甘味嗜好にどう適応すべきか?製品をローカライズするにはどうすればいいか? 1. 天然素材の自然な甘さを活用 日本人の消費者は甘いものは体に悪いという感覚を持っている、一方で甘いものは嫌いではない。要は、甘みは取りたいが砂糖は取りたくないのである。それを理解した上で商品をローカライズしていくことが重要でろう。そこで、日本では、砂糖の量を減らした上で甘さを維持するために、自然の素材の甘みに焦点を当て商品を開発するケースがある。小豆、黒ゴマ、栗などの原料に含まれる天然の糖分はほんのりと甘く、日本人の目から見ると健康的で糖尿病の原因にもならず、美容にもよいとされている。これらは日本人にとって馴染み深い食材であり、日本のデザートにもよく登場している。(小豆などの場合は砂糖が多く添加されていることもあるが。)通常砂糖を多く使用する和菓子屋でさえも、自然の豆の甘さを引き立て、砂糖の使用量を制限する和菓子を開発し始めている。 日本茶そのものの自然な甘さを商品解決に生かしているケースもある。例えば、日本のスターバックスで長く消費者に親しまれているほうじ茶ラテは、その例に当たるであろう。ほうじ茶ラテは、「優しい甘いお茶」と評されている。そのほろ苦さは控えめであるが、同時に豊かな甘い香りが漂う。さっぱりとしていて飲みやすく、とてもリラックスした気分にさせてくれる。通常のほうじ茶ラテには、シロップが入っているが、日本のカスタマーの中には、ほうじ茶そのもののほのかな甘さを楽しむためにシロップ抜きを好む人もいる。 Figure 3. スターバックスのほうじ茶ラテ (スターバックスジャパンウェブサイトより)…
-
海外在住外国人コミュニティ:“ディアスポラ”は海外進出の際のゲートウェイになる
By 鶴田 彬, 2025.01.13 はじめに 上海で新生活を始めたとき、私には友人がおらず、中国での食事にもあまり馴染みがなっかたので、多くのクラスメイトが親切に接してくれたにも関わらず、時々少し寂しさを感じていた。また、食べ物や衣服などの品物を注文・購入する際に、どの料理やブランドが自分に合っているのかを判断するのが難しかった。なので、最初の1週間のうちにキャンパス近くにあるユニクロを訪れ、必要な衣類を購入したのを記憶している。また、キャンパスライフを送る中で上海における日本人街として知られる古北地区を訪れ、日本食を楽しむことも多々あった。浦東の寮から古北に行くのに凡そ1時間以上かかったが、そこで得られる経験には価値があった。なぜなら、そのエリアは日本の小さな町の雰囲気をいくらか捉えていてくれて、日本のスーパーマーケットを訪れるたびに、懐かしい、ノスタルジックな気持ちに浸りながら、幼い頃から馴染みのある日本食品のスナック菓子や飲み物を眺めながら小一時間費やすことがよくあった。そのため、必要以上に、日本より価格は割高になるのに、商品を買ってしまうこともよくあった。また、以前は日本のアニメをあまり見ていなかったのだが、日本語の、日本的な会話のやり取りなどを楽しむために見るようになった。さらにはYOASOBIなどの日本のポップソングを頻繁に聞くようになった。 Figure 1.日本料理店が集中する日本人街の建物 上海での生活に慣れた後も、私は古北を訪れ、新しい日本食レストランを見つけたり、子供の頃に楽しんだ漫画やお菓子など懐かしいものを探したりすることが良い気晴らしになっていた。特に自分の故郷である大阪や京都などの関西エリアの日本文化を味わいたいという欲求を感じることがある。 私が経験したように、母国や故郷を離れた多くの人々はこのような感情を共有し、”故郷の味、ホームテイスト、Taste of Home“を求めているのは確かであろう。そして、これらの消費者を、とりわけ”Diaspora、ディアスポラ“と呼ばれる彼らが集まるコミュニティ・地域において、ターゲットにすることでビジネスに商機が生まれる可能性がある。グローバル化の時代において、海外に移住する人が増えるにつれ、母国の企業が新しい市場・海外市場に進出するためには、海外に移住した人々をターゲットにするマーケティング戦略が必須の戦略であろう。この記事では、ディアスポラマーケティングを説明、いくつかの成功事例を紹介し、ディアスポラをターゲットにすることから、その地でのローカル市場へどのように拡大していくかを探りたいと思う。 ディアスポラマーケティング(Diaspora Marketing) ディアスポラマーケティングは、チャイナタウンやリトルインディアとして知られる地域など、出身国以外に住む移民コミュニティをターゲットにした戦略である。受け入れ側のホストカントリーと母国側のホームカントリーとの間の文化の違いを含む、有形および無形のギャップに対処することで、商品・サービスの価値を強調し提供するマーケティングである。特に、いわゆる人々が、懐かしさを感じる商品は、このアプローチを効果的に活用できる。たとえば、上海の日本人街として知られる古北には、ラーメン屋がたくさんある。この地域は、日本の消費者が頻繁に訪れ居住することもあるため、レッドオーシャンになりつつあるものの、日本企業、特に日本の中小企業にとって、飲食店をオープンするのに最も低リスクな場所と考えられている。小規模なビジネスを行う上で、ディアスポラマーケティングは、初期マーケティングコストを抑えられる優れた戦略である。しかし、ディアスポラコミュニティの消費者から、ターゲットを現地市場に拡大する場合、コミュニティにおける全てのタイプの消費者が母国のブランドにとって理想的な顧客であるとは限らないと言われている。以下は、Harvard Business ReviewでNirmalya Kumar氏と Jan-Benedict E.M. Steenkamp氏が提案した顧客セグメンテーションマトリックスである。 Figure 2. ディアスポラ市場のターゲット顧客セグメント 出典: Harvard Business Review. Diaspora Marketing 手短にいうと、上記のセグメントの中で、企業はBiculturals(バイカルチュラル、二文化主義者)とEthnic Affirmers(民族肯定者)をターゲットにすることに重点を置く必要がある。特に、Biculturalsは、ディアスポラ市場(ホストカントリー)とホームカントリー市場の間のギャップを埋める、橋渡しをする上で重要な役割を果たすことができる。ホストカントリーとホームカントリーの双方の文化やブランドに寛容なBiculturalsは、例えば、中国人やその他の外国人の友人に、日本(ホームカントリー)のブランドを紹介するといったような自国文化を紹介する傾向が高い。 (私自身もこのセグメントに属していると感じている。)これにより、ローカル市場(ホストカントリー市場)で、口コミが生まれ話題となり、母国のブランドにおける新しい市場での認知度や人気を高めることにつながる。 多くの製品またはサービスカテゴリでディアスポラマーケティングを活用することできる。特に、食品・飲料、ファッション、化粧品、教育サービス、医療サービス、映画ストリーミングなどのエンターテインメントサービスなどが適した商品カテゴリーと考えられよう。さらに、このアプローチは、現地の消費者に正当な理由なく品質が低いと認識されることが多い発展途上国の製品・サービスが先進国市場に参入する際に特に効果的となる。 Jollibee (ジョリビー) ディアスポラ・マーケティングについて議論するとき、フィリピンで最も人気のあるファストフードチェーンであるJollibee (ジョリビー) について言及することは不可欠であろう。チキンジョイとバナナケチャップを用いたジョリースパゲッティで有名なファストフードブランドである。フィリピン国外では、地理的制限や文化的・人種的障壁により、フィリピン料理にアクセスするのが難しい場合がある。本物のフィリピンの味を提供し、フィリピン文化を讃え、懐かしさと一体感を呼び起こすことで、このブランドは、世界中のフィリピン人コミュニティの顧客と深い感情的なつながりを築くことに成功した。ジョリビーは、フィリピンに加え、ベトナム、米国、カナダ、UAE、シンガポールなど、海外在住フィリピン人が多い国に、複数の店舗を構えている。 Figure…
-
Podcast : シンガポール国立大学(NUS)の専門家が語る “シンガポール、日本、中国、オーストラリア、市場におけるBIPV(建材一体型太陽光発電)の展望”
By Qian Yuying, Akira Tsuruta, 2025.01.08 Triunityは、英語のポッドキャストを始めました!海外の市場における各業界の専門家などに随時インタビューをして、海外の第一線産業に関する詳細な情報をお届けします。ポッドキャストは基本的に英語になりますが、以下の記事で要点をまとめていますので、リスニングと同時に記事もお楽しみください。 BIPV市場のその可能性 (シンガポール、日本、中国、オーストラリア)by Triunity, 22 分 (in English) ゲストスピーカー ティアンイ・チェン博士(Dr. Tianyi Chen)、シンガポール国立大学所属 こちらのエピソードでは、シンガポール国立大学博士課程のティアンイ・チェン博士(Dr. Tianyi Chen)を特別ゲストとして招き、シンガポール、中国、オーストラリア、日本におけるBIPV(建材一体型太陽光発電)の市場展望と参入ポイントについて詳しく議論しました。チェン博士は、シンガポール国立大学の建築学の博士号を取得、シンガポール太陽エネルギー研究所の研究者であり、古木造建築物向けの太陽光発電プロジェクトの重要なメンバーである。同時に、シンガポールに自身の太陽光発電会社Power Facadeを設立し、プレハブ式カラー太陽光発電パネルの設計と生産を行っています。(https://www.powerfacade.net/)国内外を問わずBIPV市場に参入し、競争の激しい市場でリーディングポジションを維持したいと考えている BIPVサプライヤー、インテグレーター、投資家にとって必聴のエピソードとなっています。 今エピソードの内容:4つのキーポイント 01 シンガポール: 政府はプレハブBIPVを精力的に推進しており、カラー太陽光発電パネルの市場の見通しは良好 (注釈: ただし、現在のシンガポールにおけるBIPVの防火要件は比較的厳しい) シンガポールのBIPV市場についてどう思いますか? チェン博士:シンガポールは BIPVに対して非常に厳しい防火認定の取得を課しているため、シンガポール市場は非常に重要だと思っています。一度ここで認定を取得すれば、他の市場にも進出できるようになります。太陽光発電を紹介するのに非常に良い国と考えられ、政府も企業もこの市場に大きな注目を集めていることでしょう。 シンガポールではBCAなどの政府機関がプレハブ建築を推進しています。シンガポールでは、地震や洪水の問題がないため3Dモジュール式建物が非常に人気があります。その理由は、3Dモジュール式建物は、オフサイトで事前に完成させ設置できるため、シンガポールで将来的に非常に高額となる人件費を節約できます。また、私は関連する他のスタートアップのオーナーも何人か知っていますが彼らは、例えばシンガポールで実証を行って、ベトナムやタイで製品を応用しようとしています。 シンガポールは、グリーンビルディングとネットゼロビルディングのリーダーであり、多くのビルには垂直緑化や屋上太陽光発電が導入されている。これらの技術の中で、BIPVは近年の新しいパッシブ設計に当たると思われます。現在シンガポールではどのように使われているのでしょうか?シンガポールに BIPV建物の例はありますか? チェン博士:現在シンガポールで、多くの人からこのような、「BIPV製品はありますか?」、または、「既存のBIPV建物はありますか?」といったような質問を受けますが、実際には、建物のファサードに太陽光発電を設置する事例はまだ十分ではありません。 2022年9月以降、シンガポール消防署 (SCDF) は、新しい厳格な火災安全規制を発行しました。したがって、太陽光発電パネルの設置は、IECおよびISOの規制だけでなくシンガポールSCDFの現地の火災安全規制にも適合する必要があります。そのため、1 年半が経過した現在まで、火災安全規制を遵守できたのは、中来木(苏州)光伏有限公司…
-
中国カフェチェーンの海外進出“Grab-and-Go”でシェア拡大を狙え
by 鶴田 彬, 2024.10.25 はじめに:様変わりした中国のコーヒー事情 私が2017年に、ビジネススクールに留学する為、上海へと渡航する際に、日本人の先輩学生が日本からインスタントコーヒーを持ってくるといいよと勧めてくれた。理由としては、日本でインスタントコーヒーを購入する方が、中国で購入するよりコストを抑えられたからだ。また、キャンパス付近に、カフェチェーン店はスターバックスしかなく、一杯あたり30-40元(約600-800円)したので、懐事情の厳しい私費留学生にとってなかなか手が出せないものであった。2017年の夏頃の上海では、日本同様にタピオカティーブームが起こっており、グループワークの最中にクラスメイトがよくデリバリーで注文していたのを覚えている。しかし、2018年にLuckin Coffee (ラッキンコーヒー)の登場が、彼ら彼女らの習慣に変化を与えることになった。キャンパス生活2年目に突入する頃、授業中にクラスメイトからメッセージが送られてきて、Luckin Coffeeのグループ注文に参加するかしないかを聞かれた。これが、私のLuckin Coffeeとの初めての出会いであり、グループオーダーのディスカウントを使用することで、一杯あたりの価格が10−20元(約200-400円)になった。それ以降、価格が下がったことで、以前より頻繁にコーヒーを注文するようになり、ラテやアメリカーノを、授業中に注文し休憩時間に配達を受け取るといったスタイルが確立した。 市場全体を見てみるとデータは様々であるものの、CBNデータによると、中国で調査を実施した対象において、多くの消費者が、現在、週に1回コーヒーを飲んでおり、約25%が毎日少なくとも1杯のコーヒーを楽しんでいると報告されている。そして、中国の消費者は、コーヒーを単なる眠気覚ましといった機能的な飲み物としてではなく、喜びの源として捉えるようになりつつあり、中国の消費者にとって今後ますますコーヒーがリラックスの手段として広がりを見せていくだろうと報告されている。 Figure 1. 中国における消費者のコーヒー飲用頻度 Data source: CBNData 2023 April coffee drinker survey, “How often do you drink coffee in the past six months?” そして、私は、卒業後も上海に残ることになるのだが、それからより多くのカフェチェーンを目にすることになった。美団データによると、2023年において、上海には8,530店舗のカフェがあり、世界で最もカフェが多い街となっている。Luckin Coffeeやスターバックスだけでなく、Manner Coffee(マナーコーヒー)やCotti Coffee (コッティコーヒー)が私たちの目に飛び込んできた。 Figure 2. 2021-2023年における中国本土のコーヒーショップ数推移…
-
東南アジアのもう一つの入口:タイでのバイオマスと医薬分野における商機
by 钱 俞颖、2024年9月30日 キーポイント タイといえば、金色に輝くお寺、にぎやかな夜市や、絶えない各国の観光客を思い浮かべる人も多いだろう。私たちのイメージでは、タイはどこも活気にあふれている。しかし、意外なことに、タイは現在、中度高齢化社会に入っており、年齢の中央値は39歳で、ASEANではシンガポールの42歳に次ぐ高齢国だ。言い換えると、人口ボーナスが徐々に消え、経済が停滞し始めている。活発な表現とは裏腹に、転換を急ぐタイ経済が、そこにはある。 それでも、人口規模が大きく、消費力が強く、オンラインルートが比較的成熟しているため、地政学的リスクを回避することに基づいても、タイは依然として企業が東南アジアに進出する上で、第一選択の目的地の一つと言える。本文は私達のタイに対する研究と洞察に基づいて、経済発展の転換の角度からタイ市場の特徴と投資機会を整理する。 生暖かいタイ経済、改革が進む時 IMFのデータによると、2023年のタイのGDPは約5,150億ドルで、世界25位となり、インドネシアに次ぐASEAN2位の経済規模を持つ。しかし、2015年から現在まで、タイのGDPの平均成長率は1.9%前後で、マレーシアの3.9%、インドネシアの4.2%、ベトナムの7%を下回っており、ASEANの平均値4%を下回り、ASEANの中で経済成長が最も緩やかな国の一つである。 経済構造は比較的多様だが、タイ経済は国際市場に依存し過ぎており、タイの輸出はGDPの約65%を占めている。コロナ禍で、貿易、観光業が阻害され、タイのGDP成長率は6.1%低下し、いまだコロナ発生前の水準に回復しておらず、ASEAN諸国の中で経済の停滞が最も深刻な国の一つである。さらに深刻な人口高齢化も合わさって、タイ政府も着実に焦り始めていると見え、タイ経済発展の新たなエンジンを構築することを急がなければならない状況である。 そこで、タイ政府は東部経済回廊計画(EEC)とタイランド4.0戦略を通し経済の転換を模索している。単純な農業、生産製造からハイテク、新エネルギー、高付加価値サービスなどの産業に転換したい考えだ。これらの産業は、外資企業にとって比較的有利な産業であると言えよう。タイ投資促進局(BOI)が発表した10大外資誘致分野では、外資企業に対して、課税、土地所有権、ビザの利便性、外貨送金などにおいて、一連の優遇を提供している。 改革の下でどのような機会が訪れるのか? この記事では、2 つの領域を選択して紹介しようと思う。 バイオマスエネルギー タイは、ASEAN諸国の中で最も電力消費量が多い国で、エネルギーの純輸入国であり、他国からのエネルギー輸入に大きく依存している。地元の炭鉱や石油資源は乏しく、天然ガス資源は豊富だが、継続的な開発により埋蔵量は大幅に減少している。2022年には、タイは天然ガスの約38%、石油の約92%を輸入する予定と報告されている。主要なエネルギー源(総エネルギー消費量の68%を天然ガスが占める)である、国内の天然ガス生産量の減少により、現在、タイは再生可能エネルギーの開発に積極的に取り組んでおり、タイ政府は総消費量に占める非水力再生可能エネルギーの割合を2036年までに30%に増やす計画を立てている(2022年には約13.8%となる)。 タイの風力発電と地熱エネルギー資源は豊富ではないので、太陽光発電に加えて、バイオマスエネルギーについて言及する必要がある。タイ自体は大規模な農業国であり、広大な農地と森林地帯があり、多数の米、サトウキビ、キャッサバ、アブラヤシ、ヤシの木が栽培されている。さらに、政府による不動産開発の活発化により、大量の都市ゴミ(MSW)も重要なバイオマスエネルギー源の一つとなっている。政府は、年間4,000万トンのバイオマス原料が利用できると推定しており、安価なバイオマスが大量に得られるため、タイではバイオエネルギー発電が再生可能エネルギー発電の最大の割合を占めており、太陽光発電の約3倍となっている。 中国企業に関して言えば、バイオマス発電やバイオガス発電を開発しており、これらの中国企業は既にタイ市場に参入している。 2007年以来、杭州锦江、中国电工、三峰环境、華西能源(华西能源)、云南水务などの中国企業がタイの廃棄物発電プロジェクトへの投資に参加している。 2022年においては、中国能建がタイの製糖工場とバイオマス発電所を統合する包括的なプロジェクトに署名した。 しかし、政策を見るに、タイ政府が外国投資を誘致したいのは、非発電型バイオマス利用である。タイ投資委員会(BOI)は、バイオテクノロジー産業を投資を奨励する産業として挙げており、BOIが発行した投資促進プロジェクト申請ガイド2023によると、「バイオマス液体燃料、バイオマス成型固体燃料、バイオプラスチックを生産するA2企業には優先的な投資権益が与えられる」とされ、8年間の法人所得税及び機械原材料の輸入税の免除、その他税金以外にも優遇権利や利益を享受できる。 バイオ燃料の分野では、中国のハルビン電気国際社(哈电国际)がタイのキャピタル・ワン・エンタープライズ社とチャチューンサオ県パノムサラカム地区に年間生産量1,420万リットルのキャッサバベースのエタノールプラントと100MW複合サイクル発電所を建設するEPC契約を締結した。また、日本のビール会社サッポロホールディングスは、タイのPTGエナジーに第1.5世代キャッサババイオエタノールの生産をする上で技術供与している。さらに、住友商事は、サトウキビバガスを原料として使用するバイオエタノール(E2G)生産プラントを2025年までに建設する予定である。 タイは、2026 年から持続可能な航空燃料(SAF)の使用量を総燃料消費量の1%に増やす計画を持っており、SAF生産のためのG+FtおよびAtJの生産経路は、タイでより多くのアドバンテージを持っていると考えられる。ただ、現時点においては、タイのほとんどのSAFプロジェクトは、他地域同様に、使用済み燃料・食用油を使用したHEFA生産経路を利用しており、 地元石油会社Bangchakは 2022年にSAFの試験運用を開始し今年中には商業運転を達成する予定である。 Bangchakより では、バイオプラスチックに目を向けてみよう。現在、タイは世界で第2位のバイオプラスチック生産国であり、その内バイオプラスチックの90% がイタリア、オランダ、日本、韓国、米国などの国々に輸出されている。タイは、ASEANにおけるバイオプラスチックの中心地となることに尽力しており、その年間プラスチック生産量は約95,000トンに上り、地元メーカー達は、今後数年間で、さらに75,000トンの生産量を増加する予定であると、タイがバイオプラスチックペレットの年間生産量の増加を目指していることが明らかになった。今後、生産量は数年間で375,000~400,000トンに増加する見込みである。 そんな中、海外企業の活躍も見られる。2018年、Total社が50%、Corbion社が50%出資する合弁会社Total Corbion PLAは、ラヨーン県のバイオプラスチック工場での生産を正式に開始すると発表した。このプロジェクは、現在、タイ最大のバイオプラスチックプロジェクトであり、サトウキビシロップを原料として使用し、年間75,000トンのポリ乳酸(PLA)の生産能力を持つ。さらに、ブラジルのバイオプラスチック大手Braskemは、タイの化学会社SCGと合弁会社を設立し、数年以内に年間生産能力20万トンのバイオエチレン生産プラントを建設する計画である。 Vietnam Plusより バイオマスはエネルギー密度が低いため、原料の収集距離を一定範囲内に収めることができないと、収集、加工、輸送コストが高くつくという欠点を持つ。裏を返すと、今後、供給と輸送の問題が解決できれば、タイのバイオマスエネルギーの潜在力はさらに発展する可能性がある。 ヘルスケアと医薬品 タイの現在のヘルスケア・医療市場の特徴には、主に医療ツーリズム、美容外科、美容医療、生殖補助医療、革新的医薬品の臨床試験などが含まれる。BOI の「投資ガイド2023」によると、高品質の医療の生産に携わる企業が含まれ、ハイテク医療機器、医薬品有効成分(API)、標的治療薬、専門医療センターは、法人税の8年間の免除、機械や原材料の輸入税の免除や、その他の税金以外の優遇措置としてA2企業投資奨励金を享受できる。 中国の革新的医薬品会社Junshi Bioscience,の李寧(李宁)副会長へのインタビューによると、現在、東南アジア市場には革新的な医薬品が比較的少なく、東南アジアで欧米企業が販売する医薬品は主にジェネリック医薬品であり、全体としてはジェネリック医薬品が主流となっている。その結果、一部の中国の製薬会社は、東南アジアで比較的手頃な価格で革新的な医薬品を発売する前に、ヨーロッパと米国で高水準の登録を完了することを選択している。また、東南アジアの一部の国では、漢方薬の認知度が高く、2022年には上海医药がタイのバンコクに会社を設立し、医療機器や革新的な医薬品、バイオ医薬品をタイ国内に導入している。昨年、Junshi Bioscienceは、Kanglindaと合弁会社を設立し、タイおよび他のASEAN諸国8カ国でPD-1モノクローナル抗体の開発と商業化に協力している。PD-1モノクローナル抗体は主に、感染率の高い上咽頭癌の治療に使用される。加えて、今年6月、アストラゼネカは、NCDsへの取り組みに重点を置いた生物医学イノベーションを推進するため、2024年から2026年までの今後3年間でタイに約62億バーツ(約1億6,850万米ドル)を投資すると発表した。…
-
シンガポール: 東南アジアの脱炭素ハブ
To achieve carbon neutrality, Singapore will need to source 30% of its renewable energy from external suppliers in the future. With the increasing popularity of renewable energy sources, such as distributed photovoltaics, the grid system has become unstable. Foreign demand-side…
-
東南アジアへの進出: 適切な国の選択と現地での補助金 (Part 1)
The South East Asian market have been attractive for global companies in the recent years. In this blog, we introduce investment opportunities in Malaysia and Indonesia.
Latest Posts
- 京都から世界へ!中国人気カフェ「M Stand」が東山に初上陸、%Arabicaの成功に続くか?
- 【2025年版】シンガポール飲食業の規制ガイド:外国企業が知っておくべきポイント
- 新式茶のグローバル展開: サプライチェーンの最適化が成功の鍵 (MIXUE, HEYTEA, CHAGEE, ChaPanda)
- MIXUE (蜜雪), HEYTEA (喜茶), Chagee (霸王茶姫), etc. 中国の新式茶とは?-新式茶市場における新たなトレンドを分析-
- 新式茶会の先駆者HEYTEAは日本の消費者をインスパイアできるのか?-日本初、HEYETA大阪店を紐解く-
- “砂糖は嫌いだが甘さは好き”-ワガママな日本人消費者の好みにどう対応するか
- 海外在住外国人コミュニティ:“ディアスポラ”は海外進出の際のゲートウェイになる
- Podcast : シンガポール国立大学(NUS)の専門家が語る “シンガポール、日本、中国、オーストラリア、市場におけるBIPV(建材一体型太陽光発電)の展望”